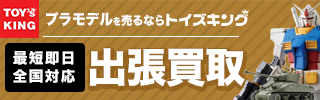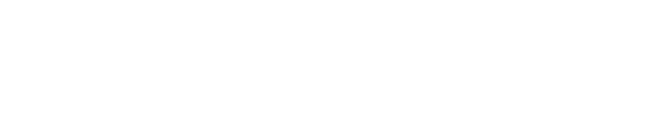【ZIックリガイド】PR含

昭和の懐古録
「ローメンコ」時代を築いた昭和レトロな雑貨たち
古い日本映画などに登場する昭和レトロなインテリアや雑貨には、どこか心癒されるノスタルジックな魅力があります。本記事は、昭和の玩具(おもちゃ)「ローメンコ」を通して昔を懐かしむ昭和の懐古録です。ー
1980年代末期(昭和60年代)駄菓子屋がまだ存在し、子供たちの間でも、まだメンコが遊ばれていました。中でも、角型ではなく丸型で、とても小さなサイズの「ローメンコ」と呼ばれる種類が流行っていました。
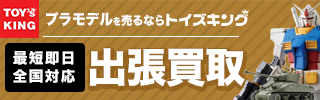
昭和レトロな玩具「ローメンコ」

「ローメンコ」予備知識メモ
「ローメンコ」と言う名の由来は、製造元が明らかにしていないのでハッキリとしたことは言えませんが、メンコに蝋が塗られていることから来ていると思われます。つまり漢字で表記するなら「蝋面子」ということになります。当時のメンコは、多くが無版権で製造されており、地域の小規模な業者が製造を手がけていたことが多かったため、現時点で信頼性の高い公的資料や文献による確認はできませんが、ローメンコは、紙製のメンコによる遊びが最盛期だった1950年代(昭和中期ごろ)に登場したと推測されます。
このメンコは多くの場合、小銭の束のように束ねられ、側面を蝋で固めた上で紙に包まれ、一束5円〜20円という価格で販売されていました。メンコの製造元は、玩具メーカーに限らず、駄菓子屋メーカーや地方の紙製品業者も関わっており、代表的なメーカー名としては、天田玩具製作所などがありました。ー「ensky(元・天田玩具製作所)」
「ローメンコ」その出回り方
販売用の箱や包み紙に表記されていた「ローメンコ」及び「ロー面子」という呼び名は、子供たちの間では少し呼びづらく、「ローメン」とだけ呼ばれることもありました。(以下「ローメン」と呼称。)また、当時それぞれの地方でいろんな呼び名もあり、主に、その遊び方に由来していましたが、この記事を執筆している筆者の近辺(九州地方)では、「ピンチョコ」、もしくは「パッパ」と呼ばれていました。

ローメンのサイズは、メンコの中でも一際小さく、直径は約2cm〜3cmほど、厚さは一般的なメンコよりも薄めで、約1mmほど、100円玉硬貨ほどのサイズの、とても可愛いメンコでした。子供たちとしても、ローメンをたくさん持っていると、お金をたくさん持っているかのように得意気になりました。
メンコは昭和の時代に遊ばれた有名な玩具ですが、残念ながらローメンに関する情報だけは、Wikipediaにも、権威ある財団法人サイトにも掲載されていません。これは当時から、メンコはメンコであり、大きさや状態の違いだけで、特別に意識されるということが無かったからだと推測されます。蝋を塗られた市販のメンコがいつ発売されるようになったかなど、とくに誰も記録に留めなかったようです。ー「一般財団法人 日本玩具文化財団「おもちゃの歴史」」
\ 懐かしい漫画も電子版でスッキリ /
「ローメンコ」遊びの思い出
束ねられ、蝋で固めて売られたローメンは、一枚一枚を指で丁寧に剥がして使用されました。遊び方としては、蝋で滑りやすく加工された側面を指でつまんで持ち、力を加えて滑り飛ばして飛距離を競う、「ローメン飛ばし」と言った遊びが主流ですが、その遊び方のイメージが、販売用の箱に描かれていることもありました。ローメンよりも大きく厚みのあるメンコに、「トバシメンコ」と言われるものがあり、そのメンコには、輪ゴムを引っ掛けて飛ばすための切り込みが入っていましたが、ローメンにはそのような切り込みはありませんでした。
先述した通り、筆者の住む周辺では、ローメンは主に「パッパ」と呼ばれており、対戦相手と向き合って置いた自分のメンコに、それぞれ交代で「パッ」「パッ」と息を吹きかけて進め、「相手のメンコに乗り上げた方が勝ち」といった遊び方をしていました。そして他のメンコ遊びと同じように、勝てば相手のメンコがもらえるルールでした。朧げな記憶ですが、乗り方が微かだったり、裏返って乗った場合の勝敗は無効で、その状態から相手の次の息の吹きかけにより、両者のメンコが宙を舞い、「奇跡の逆転どんでん返し」となる、という展開もありました。このように、それぞれの地方にそれぞれの遊び方が広がりました。

「ローメンコ」刻まれた記憶
ローメンの入手は、自分で購入せずとも、分けてもらうこともありました。と言うのも、購入した際に絵柄が重複する(「ダブる」とも表現。)ことが多かったからです。また、手持ちのメンコが無く、遊びたくても勝負ができない子供たちは、代用品として牛乳瓶の蓋などを使って勝負することもできました。もっとも、蓋での参戦が認められた場合のみですが、そのようにして、まともなメンコを増やして行く体験は、ある意味、子供時代に経験できる最初の成り上がり体験だったかもしれません。
ところで、メンコに限らず昔の玩具(おもちゃ)全般に言えることですが、描かれるイラストのクオリティーや著作権感覚は今以上に適当でした。無許可でキャラクターを使用して販売することはもちろん、印刷がズレていたり、線や色塗りが雑なのも当たり前でした。特大メンコのように、豪華な景品クラスのクオリティは素晴らしいものがありましたが、ローメンはサイズも小さく低コストな商品だけに、品質は悪く、子供騙しの感は否めませんでした。しかし「バッタもん」という言葉も流行るくらい、意外と当時の子供たちはしっかり品質を見抜き、「胡散臭い玩具」として割り切って使っていました。それらの玩具も、今では昭和の良い味わいとして愛されています。
\ 眠ったおもちゃに価値がある! /
「ローメンコ」その後の歴史
ローメンはそのサイズ上、俗に「パッチン」と言われるような通常のメンコの遊び方はできませんでした。それで、飛ばすか息を吹きかけて遊ぶ以外は、主に、コレクションアイテムとして愛されました。1970年代(昭和後期)以降、メンコによる遊びも下火となり、ローメンの流通量も減少して行きましたが、時代が過ぎた後も、この「ミニサイズのメンコ」は、シールやカードに並ぶ子供のコレクションアイテムとして度々製造され、主にお菓子のおまけなどに付属されました。(※しかし、もう蝋は塗られていないので、厳密にはローメンコではなく、ミニメンコ。)
おまけのミニメンコとして比較的有名なのは、S&B(エスビー)食品株式会社の販売したスナック菓子「S&Bスナック」に付属された、ドラゴンボールシリーズのミニメンコです。このメンコの大きさは、約3cm(ドラゴンボールGTは約4cm)ほどで、ノーマルデザインに加え、子供心をくすぐる、シルバーとゴールドのデザインがありました。初期は一つのお菓子の袋に2つのメンコ入りで、これらのメンコもやはり、遊びで使うというよりはコレクションアイテムとして愛されました。

おまけとしてのミニメンコ
カルビーのポテトチップスを例として、付属したおまけのミニメンコシリーズの一例を下に記します。(※全シリーズではない。)
ファミコンキャラクター
(販売:1983年~1985年頃)
キン肉マン
(販売:1985年~1987年頃)
聖闘士星矢
(販売:1986年~1989年頃)
ドラゴンボールZ
(販売:1988年~1990年頃)
Jリーグ
(販売:1990年代後半~2000年頃)
妖怪ウォッチ
(販売:1995年~1997年頃)
他
ちなみに、ミニメンコのおまけに似た、「メガタゾ」というものもありました。これは1990年代に、フリトレーが販売するスナック菓子のおまけとして付属された、八方向に切り込みの入った直径約4.5cmの丸型メンコ風の玩具(おもちゃ)ですが、切り込み同士を連結させて飾ったり、一箇所有る大きな切り込み同士を噛み合わせて、弾力で弾いて飛ばしたりして遊べました。主に機動戦士ガンダムシリーズや、ワーナー・ブラザースのキャラクターシリーズがデザインされ、「元祖たこやき亭」や「マイク・ポップコーン」などのスナック菓子に封入され、こちらもコレクションアイテムとして人気を博しました。
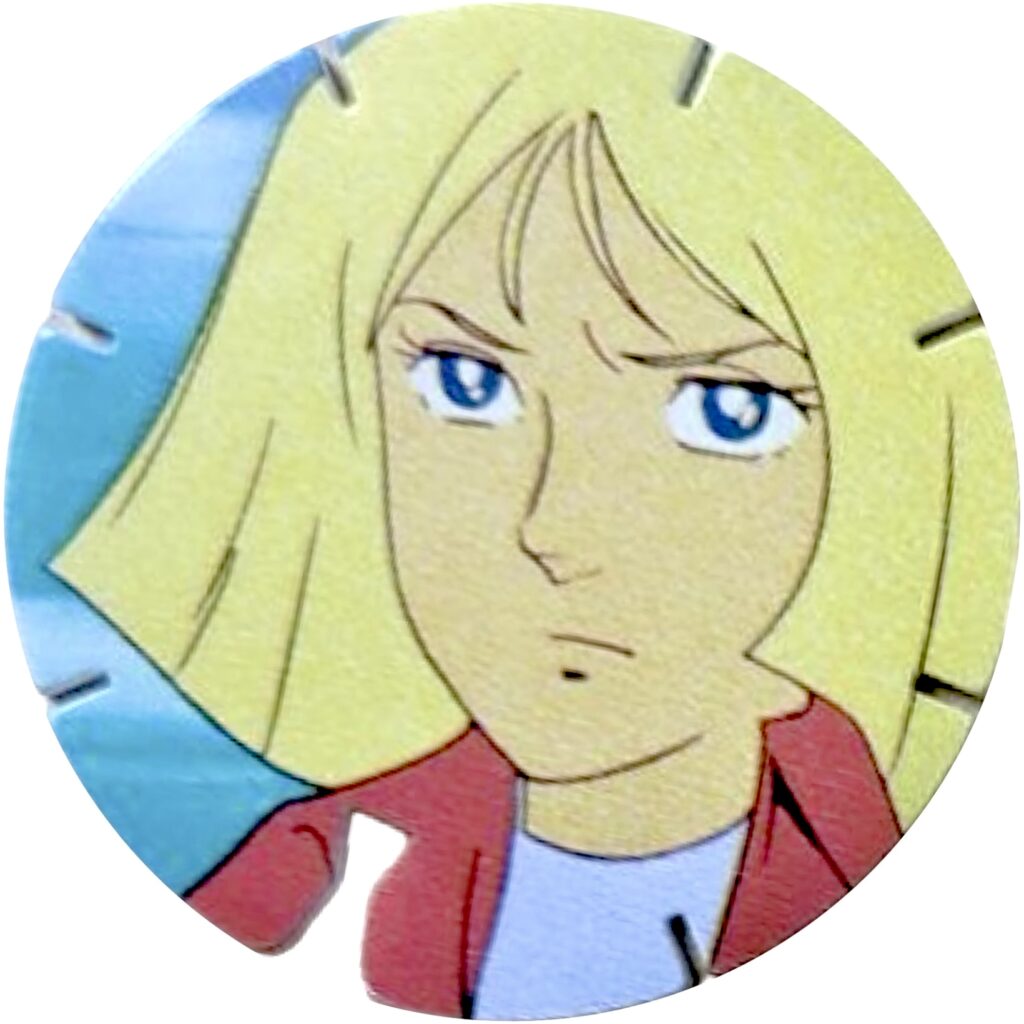
昭和レトロな玩具「ローメンコ」結び
小さくて収集欲を掻き立てる、ローメンコやミニメンコに、当時の子供たちはワクワクさせられました。筆者も鮮明に覚えている光景として、小学生のころ学校で何気に覗いた上級生のクラスに、大量に袋詰めされたローメンが置かれてあり、夢が詰まったその袋に手を突っ込み、握って帰りたい、と非常にワクワクさせられたものでした。今思えば、あれは先生に没収されたメンコたちだったかもしれません。ローメンコは、昭和を生きた子供たちをワクワクさせ、熱狂させた、本当に懐かしいレトロな玩具でした。機会があればぜひ、その懐かしいおもちゃに会いに昭和レトロの博物館などに行ってみましょう。
※本記事に画像を添付している場合、昭和期の雑貨やおもちゃを紹介し、歴史的背景を紹介する目的で記載しています。もし権利者様からのご連絡がありましたら、速やかに削除対応いたします。
時代を築いた昭和レトロな雑貨たち〜
その他の昭和レトロなおすすめ記事はこちら。
>「昭和レトロな琺瑯看板『塩・たばこ』」